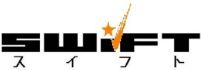コラム
column
河川構造物とは何か?河川管理の必要性や主な河川構造物と設計の基準についてわかりやすく解説します!
2023年07月14日
日本の土木の歴史の中で、河川構造物の設計や設置は重要な位置を占めています。
勾配が急で降水量が多い日本列島はしばしば河川の氾濫による水害に悩まされてきたからです。
度重なる河川氾濫への対処は現在進行形で続いています。
本記事では河川管理の必要性や主な河川構造物とその設計基準についてわかりやすく解説します。

河川管理の必要性
日本列島には大小さまざまな河川が存在しています。
河川は流れる場所によってさまざまな姿を見せます。
上流部は深い谷を刻むように流れ、V字谷を形成します。
中流部では扇状地や氾濫源を形成し、下流部では緩やかに大きく流れます。
流れる場所によって水量や水の勢いが異なるため、地域ごとで全く別な河川管理が必要です。
河川管理をしっかり行うことで、梅雨前線や台風のときでも河川氾濫を防ぎ、氾濫が発生しても被害を最小限にとどめることができるのです。
河川構造物とは何か
河川構造物とは、河川の水が河川の外に流出するのを防ぐために作る工作物のことです。
河川沿いの住民の生命や財産を河川氾濫から守るための防災施設と言い換えることができます。
河川の洪水を防ぐには河川の流路を整備する河道改修や堤防や護岸の設計・建設・強化などが必要です。
河川構造物は国が定めた設計基準があり、河川にかかわる企業はこの基準を守って工事を行っています。
また、河川構造物は定期的に検査され、耐震性能や健全度などが評価されています。
近年、高度経済成長期から1990年代にかけて建設された多くの河川構造物が大規模改修を要する時期に入っているため、計画的かつ早急な対応が必要です。
過去の河川改修とことなり、昨今はSDGsを意識した河川構造物の設置が求められています。
河川の景観や多様性を守りつつ、人々の暮らしをどのように守るべきか、新しい河川工事の必要性が増しています。
河川の区分
河川は以下の4種類に分けられます。
・一級河川
・二級河川
・準用河川
・普通河川
一級河川は国土保全上重要とされる一級水系に関わる河川で、国土交通省が指定しています。
一級河川の数は全国でおよそ14,000あります。
二級河川は都道府県知事が管理する二級水系の河川のことです。
準用河川と普通河川は市町村が管理します。
主な河川構造物と設計基準
一口に河川構造物といっても多種多様のものがあります。
その中で、今回は堤防・護岸・堰について取り上げます。
堤防
堤防とは、河川が洪水を起こさないように作られた盛土のことです。
堤防設計の基準は、川の水量が計画高水位以下のときに決壊しない安全性を有していることです。
浸透に耐える耐浸透機能、河川水の浸食に耐える耐侵食機能、地震に耐える耐震機能などの基準を設け、それらを満たすように設計されています。
土質試験やボーリング調査、物理探査などを通じて設計上の基準を満たしているか調査されます。
護岸
護岸とは、川の浸食作用から河岸や堤防を守るために作られる施設で、川に面した斜面(表法面)をコンクリートなどで覆います。
護岸には堤防護岸・高水護岸・低水護岸などがあります。
護岸は河川に最も近い部分に作られる河川構造物であるため、生態系や景観への配慮を強く求められます。
護岸を設計するときは、貴重な動植物種の生息状況を踏まえて工事を行います。
そのため、レッドリストやレッドデータブック、河川環境情報図などの活用が必要です。
近年増加しているのが大型連節ブロックを採用した護岸です。
施工性がよく、短い工期で設置できるため経済的であることや質量が大きく効果の高い護岸となることがその理由です。
水面上に露出する護岸は周囲の景観とマッチする色合いや鮮やかさであることが必要です。
素材の持つ質感への配慮も必要で設計段階でそのことを考慮する必要があります。
石を不規則に積んで、自然に近い状態にすることも可能です。
堰
堰とは、河川の水の流れを制御するため河川を横断して設置される施設です。
基本的に堤防の機能は有さず、ダムとも異なります。
堰は河川の分流地点に設置される分流堰、塩水の遡上を防止する潮止堰、河川の推移を調整したり農業・工業・生活に必要な水を取り入れるための取水堰の3つに区分できます。
堰は、洪水時に川の水を妨げないようにすることや魚道をつくることなどを踏まえて設計されます。
まとめ
今回は河川管理の必要性、河川構造物の種類や設計の基準などについて解説しました。
高度経済成長期に作られた河川構造物の多くが更新の時期を迎えている中、集中豪雨などにより各地で水害が発生しています。
過去の設計基準では防ぎきれない水害が出てきているのかもしれません。
加えて、自然環境に対する配慮も求められているため、生態系を壊さない河川構造物を設計する必要があります。
自然と人間が共存しつつ、河川周辺の住民の生命財産を守るという2つの命題の達成を求められているのが河川構造物の設計の現状ではないでしょうか。