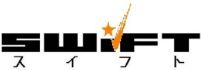コラム
column
【電力柱・電信柱】電柱の種類と違い、それぞれの役割について
2023年03月15日

電柱(でんちゅう)と電信柱(でんしんちゅう)の違い
「電柱」と「電信柱」は同じものだと思っている人が多いのではないでしょうか。
結論から言えば、電柱と電信柱は別のものです。
「電柱」は、電力会社などが、送電・配電の目的で設置・管理しているもののことです。
「電信柱」は、電話線など通信に使用するための電線を架線するためのものをいいます。
そして、「共用柱」という電柱と電信柱を兼ねたものもあります。
しかし、これらの呼び名は厳密の使い分けられているわけではなく、電柱のことを「電信柱」と呼ぶ人も多いようです。
地域によっても呼び方は違っていて、西日本では「電信棒」と呼ばれる地域もあります。
電柱には、所有者を示すプレートが取り付けられており、「東京電力」や「NTT」などと書かれています。
共用柱の場合は、プレートが複数取り付けられていますが、所有者を示すプレートは地面に近い方です。
電柱の種類と役割
電柱は、大きく3つの種類の分けられます。
電力柱
家庭に電気を送るための電線や変圧器などが架かっています。
所有者は、「東京電力」・「関西電力」などの電力会社です。
電力柱には、各電力会社の名前が記載されたプレートが取り付けられています。
電力柱の呼び名は電力会社によっても違っており、以下のとおりです。
・北海道電力…【北電柱】
・東京電力…【東電柱】
・関西電力…【関電柱】
・中部電力…【中電柱】
電信柱
インターネット・電話・光回線・ケーブルテレビなどの通信用ケーブルや光ケーブルなどが架かっており、通信基地局なども設置されています。
所有者は「NTT」などの通信会社であり、「NTT」もしくは「日本電信電話公社」のプレートが取り付けているので識別可能です。
共用柱
電線と通信線の両方が1本の柱に設置されています。
ビルや住宅が密集している地域など、電力柱と電信柱を1本1本別々に立てる場所がとれない場合に設置されます。
なお、電柱に貼り付けられたプレートを見れば電柱の所有者がわかりますが、
共用中の場合は、一番下にあるプレートに所有者名が記載されています。
電柱は、使われる素材によって分類すると以下のようになります。
設置する場所の状況に応じて最適なものが使われます。
A.コンクリ―ト柱:一番よく目にする電柱
B.木柱:木材を使った電柱
C.管柱:鉄鋼を使った電柱
電柱の主な設備
電柱を観察してみるといろんな設備が取り付けられているのがわかります。
柱上変圧器(ちゅうじょうへんあつき)
配電線の電圧を下げるための装置です。
碍子(がいし)
配電線を伝わって電柱に電気が流れないようにする設備のことをいいます。
柱上変圧器
家庭に電気を送るために6600Vもの高圧の電気を100Vまたは200Vの低圧に変換する装置です。
支線・支柱
電柱がたおれないように支え、電柱にかかる力を分散させます。
高圧配電線
電柱の高い位置に横に3本並んでおり、6600Vもの高圧の電気を運ぶ線です。
低圧配電線
100Vと200Vの電気を運ぶ電線で、高圧配電線より下の位置に、主に縦並びに3本通っています。
高圧カットアウト
雷などで異常な電流が流れた時に切り話して柱上変圧器を保護する役割を持ち、柱上変圧器の近くに設置されています。
架空(かくう)地線
電柱の先に設置され、避雷針(ひらいしん)の役目があります。
引込(ひきこみ)線
電柱から各家庭に電気を引き込むための線です。
電柱に昇って何をしている?配電工事について
「配電工事」とは、電柱や電線などの設備を建設したり改修したりする工事のことです。
配電工事には電柱の設置や外線配線工事、災害時の復旧やメンテナンス、点検工事などがあります。
これらの工事は専門資格をもつ人によって行われます。
電柱を設置する際は、まず穴掘建柱車を使って電柱を埋めるための穴を掘ります。
電柱の吊り上げ作業は、小型移動式クレーンを使って行います。
電線の配線工事には、電柱から住宅などに電線をつなぐ工事や、発電所から電柱までの電線をつなぐ外線配線工事などがあります。
さらに、無電柱化を進めるために、共同溝や地中ケーブルを利用して地中配電線工事を行うこともあります。
ライフラインを支える電柱
ライフラインには道路、上下水道、鉄道、導水路、通信、電話送電線などがあります。
そのすべてに関わるのが「電気」であり、その電気を家庭に送るために「電線」があり、その電線の架け渡しをしているのが電柱です。
電柱があるので、人々は毎日不自由しないで電気を使用することができます。
電柱はライフラインを支える大切な設備といえるでしょう。
日本には現在、3600万本もの電柱があるといわれています。
景観を高める目的などから無電柱化も検討されていますが、電柱は減る様子はありません。
建設にかかるコストパフォーマンスなどを考えると、しばらくは電柱とお付き合いは続きそうです。
※弊社では電柱の移設や撤去はおこなっておりません。