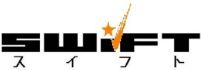コラム
column
地中配線の施工方式の種類は?メリットやデメリットも解説
2023年02月22日
高いところに電線を張って電気を送る架空方式が、送電経路としては一般的です。
しかし、近年は地中配線も増えています。
無電柱化をご存知の方も多いでしょう。
無電柱化も、電線を地下に通す地中配線です。
今後は、地中配線がさらに増えていくと考えられます。
この記事では、地中配線の施工方式についてお伝えします。
また、地中配線のメリット・デメリットも解説するので、地中配線について理解を深めたい方はぜひ参考にしてください。

地中配線とは?身近な場所の地中配線
地中配線とは、道路の下などにケーブルを通す配線方式です。
冒頭でもお伝えした通り、無電柱化も地中配線です。
さらに身近なところでいうと、住宅の門や庭、カーポートなどに取り付けられた照明や電灯が該当します。
地中配線は、屋外の建物から離れた場所にある照明設備に電気を通すためによく用いられます。
地中配線の施工方式の種類
地中配線の施工方式は、大きくわけて3つあります。
● 直接埋設式
● 管路式
● 暗渠(あんきょ)式
どのような場所に地中配線をするかによって、適切な方式を選択しなければなりません。
ここでは、3つの施工方式をそれぞれ解説します。
低コスト・短工期な「直接埋設式」
直接埋設式は、ケーブルをそのまま埋める方式です。
直接といっても、ケーブルが損傷しないように保護しなければなりません。
トラフと呼ばれるU字型の溝やボックスに収めたり、強固な板で保護をした状態で埋設たりします。
直接埋設式は、このあと紹介する2つの方式と比べると、工事費が安く、工期が短い点がメリットといえるでしょう。
一方で、ケーブルの損傷を防ぐために、地上からの衝撃を受けにくい深さに埋めなければなりません。
埋める深さの規定がある点がデメリットです。
再掘削が困難な場所にも有効な「管路式」
管路式は、鉄筋コンクリート管や鉄管、強化プラスチック管などを地中に埋めて、管に空いた穴にケーブルを通す方式です。
管路式は、何度も掘削工事できないような場所で採用されています。
ケーブルの本数が多いときや、交通量が多い道路などで使われます。
ケーブルの増設や撤去が比較的簡単に行える点や、しっかりと管で保護されているので、外傷を受けにくい点がメリットです。
しかし、ケーブルを通す穴には十分なスペースがないため放熱が悪く、流せる電流の大きさが制限されてしまいます。
機能的な「暗渠(あんきょ)式」
暗渠式は、暗渠と呼ばれる四方を強度の強いコンクリート壁で囲まれた密閉空間を地下に埋設して、その中にケーブルを納める方式です。
暗渠は人が入れる大きさで、正方形や長方形、アーチ形などがあります。
暗渠式は機能面で優れており、ケーブルの増設・撤去、メンテナンスがしやすい点がメリットです。
一方で、工事費が高く、工期が長い点がデメリットといえるでしょう。
地中配線のポイント
地中配線工事をするには、電気に関する法令を守らなければなりません。
配線を地上の衝撃から守るために重要です。
ここからは、埋設する深さと使用する電線を紹介します。
埋設する深さは決まっている
地中配線は、車両やそのほかの重量物の圧力に耐え、掘削工事などの影響を受けないようにしなければなりません。
そのため、経産省では、埋設の深さに関する基準が定められています。
車両などの圧力を受ける恐れがある場所とそうでない場所で、埋設する深さが違うので確認しておきましょう。
重量物の圧力を受ける恐れがある場所では1.2m以上、重量物の圧力を受ける恐れがない場所では、0.6m以上の深さに埋設する必要があります。
ただし、圧力に耐えられるような施設の場合は、この規定通りではありません。
例えば、FEP管(地中埋設のための保護管)を使用する場合がそれにあたります。
車道の地下なら0.8m以上、歩道なら0.6m以上、一般住宅構内や集合住宅、学校、公園などであれば0.3m以上となっています。
使用する電線
地中配線に使用する電線は、ケーブルでなければなりません。
ケーブルとは、電気を通す素材(導体)を電気を通さない素材(絶縁体)で覆った複数の電線を、外皮(シース)でさらに覆って一つに束ねたものです。
外皮によって中の導体がさらに保護されるため、安全性や耐久性に優れています。
地中配線には、絶縁電線は使用できません。
絶縁電線とは、銅などの電気を通す導体が絶縁体で覆われたものです。
OW線、IV線、DV線などがあります。
地中配線で使われる主なケーブルは、VVFケーブル、VVRケーブル、EM-EEFケーブル、CVケーブルです。
| ケーブル | 特徴 |
| VVFケーブル | 外側を塩化ビニルで覆っている平型のケーブル
15A程度の照明やコンセント回路などの屋内配線でよく用いられるが、屋外や地中にも使える |
| VVRケーブル | VVFケーブルと同様で、丸型タイプ
低圧屋内配線でよく用いられるが、屋外や地中にも使える |
| EM-EEFケーブル | ポリエチレンで外側を覆っている平型のケーブル
VVFケーブルをエコケーブルとして改良したもの VVFケーブルと比べて柔軟性がないため、施工が難しくなるうえに高価である 屋内、屋外、地中に使える |
| CVケーブル | 架橋ポリエチレンで導体を覆い、外側にビニルシースを施したケーブル
送電、配電、配線など幅広い場面で使われる |
地中配線で使用できる電線を覚えておきましょう。
地中配線のメリット・デメリット
地中配線のメリット、デメリットをそれぞれ解説します。
メリットには、以下のようなものがあります。
● 景観がよくなる
● 感電リスクが少なくなる
● 天候不良による影響を受けにくい
電線を埋めると、人の視界に入らなくなり、容易に触れる危険もありません。
そのため、景観が保たれ、感電するリスクも少なくなります。
また、強風や大雨、台風、積雪など天候の影響を受けにくいのもメリットです。
天候不良による停電や断線の心配がありません。
デメリットは、以下のようなものがあります。
● コストが高い
● 工期が長い
● トラブル時の復旧に時間がかかる
施工方式によっても異なりますが、建設コストが高く、工期が長めです。
また、トラブルが発生した際は目視確認ができないため、異常がある箇所の発見が難しく、復旧までに時間を要します。
まとめ
地中配線の施工方式についてお伝えしました。
地中配線の施工方式は、直接埋設式・管路式・暗渠(あんきょ)式の3つです。
地中配線にすると、景観がよくなり、感電するリスクが減るなどのいい面があります。
一方で、建設コストが高く、完成までに時間がかかるため、一般的な工事とはなっていません。
今から地中配線工事の知識を深め、無電柱化にも対応できるようにしましょう。