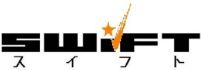コラム
column
無電柱化工事のコスト高解消!工事の概要と低コスト工法を紹介!
2022年12月18日
美しい景観と防災効果、通行の安全も確保されてメリットの多い無電柱化ですが、国内での無電柱化工事は進んでいないのが現状です。
無電柱化工事の進まない主な理由はコスト高によります。
ここでは、無電柱化工事の概要と現状の解説、そして近年模索され始めた低コストでの無電柱化工事を紹介します。

無電柱化工事の概要
無電柱化工事は「電線類地中化」と「電線類地中化以外の無電柱化」に分けられます。
いずれも読んで字のごとくの方法です。
このうち、「電線類地中化」は負担の割合によって4種類に、「電線類地中化以外の無電柱化」は2種類に分けられます。
| 電線類地中化の工事 | 「共同溝方式」
「自治体管路方式」 「単独地中化方式」 「要請者負担方式」 |
| 電線類地中化以外の工事 | 「裏配線」
「軒下配線」 |
日本での主流は「共同溝方式」
「共同溝方式」とは、電力線や通信線等のライフラインをまとめて道路地下に収容する工法です。
地下配管の費用はすべて道路管理者が引き受け、電線管理者は地上部のトランス部分の費用を負担します。
工事には、地権者や多数の業者との工事段階ごとの交渉、既存物件の撤去や移設なども含まれるため、長い期間を要します。
無電柱化が進まない要因の一つといえるでしょう。
メリットはメンテナンスが容易な点、デメリットはコストの高さと狭い道路では工事ができない点です。
自治体管理の「自治体管路方式」
自治体が管理する「電線類地中化」工事です。
設備の材料費と工事費を地方公共団体が、そのほかの費用は電線管理者が負担します。
第二期電線類地中化計画(1991~1994)当時には無電柱化工事の20%を占めていました。
工事方法は「共同溝方式」とほぼ同じ管路方式が用いられ、道路占用物件として地方公共団体の管理下におかれます。
「単独地中化方式」と「要請者負担方式」
電線管理者である電力会社自らの出資・管理による無電柱化工事を「単独地中化方式」といいます。
第一期電線類地中化計画(1986~1990)以前より実施され、計画推進当時には全工事の80%を占めていました。
その後、新電線類地中化計画(1999~2003)には3%に減少、今なお低迷が続きます。
「要請者負担方式」は無電柱化を要請した企業や個人が全額費用負担します。国や自治体によって優先度が低いとされた箇所等に用いられます。
日本の無電柱化工事は進んでいない
1980年代から国策として進められ、2021年の東京オリンピック前にも声高に叫ばれた「無電柱化」ですが、普及は一向に進んでいません。
現状としては東京23区内でさえ8%程度、顕著な例としては大阪・兵庫の都市圏くらいで、5%を超えるのは大阪市と名古屋市のみとなっています。

引用:『国土交通省 政令市の全道路の電線・電柱のない道路延長の割合(令和2年度)』
無電柱化100%のロンドン・パリ・香港など海外との差は歴然としています。

引用:『国土交通省【欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状】』
日本で無電柱化工事が進まないのは高コストが原因
日本での無電柱化工事は主に「共同溝方式」が用いられてきました。
容易なメンテナンスと安全性のメリットが大きい反面、大がかりな工事のコスト高がネックとなっています。
その埋設費用は1kmで3.5億円です。
これに地上工事の1.8億円が加算され、合計5.3億円かかるといわれています。
対する海外では「直接埋設法」が主流、1kmあたりの費用は8千万円です。
差額だけで、「無電柱化」普及の違いに納得してしまいます。
低コストの無電柱化工事4選
他国と比較するまでもない圧倒的なコスト高の解消のために、低コストでの「無電柱化工事」の試行錯誤が続いています。
海外で主流の「直接埋設方式」の普及、「浅層埋設」「小型BOX方式」の推進、「電線地中化以外の方式」である「軒下配線と裏配線」について解説します。
圧倒的な低コスト!「直接埋設方式」
常に比較される海外とのコスト差は「共同溝工事」と「直接埋設方式」との工法の違いそのものです。
それぞれの1kmあたりのコストは「共同溝工事」が5.3億円に対し、「直接埋設方式」はわずか8千万円と、格段に違います。
工期も短く、最もコストのかからない方法ともいわれる一方、埋設ケーブルの保護機能が問題視されています。
断線の可能性、またはその復旧対応が困難な点がデメリットです。
工期を短縮できる「浅層埋設方式」
狭い道路やほかの埋設物の多い箇所で施工しやすい工法です。
地中の浅い位置に埋設するため、短い工期でコストを抑えられるメリットがあります。
加えて、リサイクル部材の活用など、いっそうの低コスト化へ向けた取り組みを展開中です。
デメリットとしては、ほかの埋設物を傷つけてしまう可能性を指摘されています。
コンパクト化でメンテナンスが簡単「小型BOX方式」
「共同溝工事」をそのままコンパクト化したのが「小型BOX方式」です。
狭小道路でも施工可能で、京都市先斗町での施工例があります。
メンテナンスも容易ですが、コスト削減に関しては、あくまでも「共同溝工事」に比較して低減化されてきた範囲です。
さまざまな面で最もバランスのよい方法として、施工経験を重ねながら、よりコスト削減できる方法を模索しています。
超低コストの「裏配線」と「軒下配線」
掘削工事の要らない、超低予算でできる「地中化以外の無電柱化」工事が「裏配線」と「軒下配線」です。
「裏配線」とは、趣のある街並みや歴史的建造物の立ち並ぶ区域の景観を損ねないよう、表通りの電柱や配線を撤去し、裏通りに配線する工法となります。
「軒下配線」は読んで字のごとく軒下に配線して目立たなくする工法です。
「裏配線」と「軒下配線」のいずれも、沿道世帯主の合意を必要とします。
まとめ
「無電柱化工事」は、住民の理解と業者や自治体との交渉から始まり、計測と掘削を繰り返しつつ通信ケーブルと電線工事、それぞれに長い期間を要します。
コストがかかるのも当然といえますが、近年は、埋設でない「無電柱化工事」や低コスト工法の技術開発も進み、導入エリアが拡大してきました。
さらなる低コスト化も模索され、いっそうの普及が期待されます。
※弊社では電柱の移設や撤去はおこなっておりません。