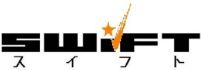コラム
column
電線地中化が進まない4つの要因!低コスト工法と成功事例の紹介も
2022年12月25日
政府による電線地中化への取り組みは 1986年の第一期計画より継続し、2016年には「無電柱化の推進に関する法律」が施行されました。
それにもかかわらず、最も導入の進んでいる東京23区内でさえ8%程度の現状です。
ここでは、電線地中化の推進を阻んでいる要因を探り、メリット・デメリットと比較検証します。
最大の懸念事項であるコスト問題を解消する工法と、電線地中化に成功した美しい街の紹介も併せてご覧ください。

日本の電線地中化が遅れているのは4つの要因による
日本の電線地中化の現状は、東京23区の8%の数値を出すまでもなく、周囲を見渡しただけで一目瞭然です。
慣れ親しんだ風景でもあり、それもまた電線地中化を阻んでいる要因の一つといえるでしょう。
「電線地中化」を阻んでいる4つの要因を、メリット・デメリットとは異なる視点で解説します。
コストへの懸念
電線を地中化する工事には巨額の費用がかかり、電柱による電線敷設の3~10倍といわれています。
1kmあたりの概算費用は1~5億円です。
費用負担は工事方法によって異なりますが、日本で主流となっている「共同溝方式」では、国・地方自治体・電線管理者の3者で分担します。
さまざまなメリットから国が主となって推進してきた「電線地中化」ですが、一方では、多額の税金投入への批判的な意見も出ています。
その税金を納めているのは紛れもない、その道を往来する、われわれ庶民です。
国の裁量が問われるところです。
昭和の原風景的安心感
日本では、雀や鳩の留まる電線、犬のマーキングスポットとしての電柱に安心感を覚え、むしろ電線のない空に物足らなさを感じてしまう方も少なくありません。
昭和の戦後復興からずっと馴染んできた原風景といえるでしょう。
その復興の一時的措置としての電線・電柱の乱立だったのですが、そのまま高度成長期に突入してしまい、さらなる乱立を呼び込んでしまったのが現状です。
本来の目的に立ち返った、令和の感性への期待が高まります。
及び腰になる電線管理者
オール電化住宅やEV車の普及により、電力需要はさらなる高まりをみせています。
世帯や周辺自治体を挙げての電気容量の増加も視野に入れたメンテナンスが必要でしょう。
しかし、狭い道路や「共同溝方式」以外の工法による地中化のメンテナンスは困難、かつメンテナンス費用もかさみます。
初期投資、維持メンテナンス費用を考えると電線管理者が及び腰になるのも頷ける話です。
難航する地主との交渉
張り巡らされた電線の種類はさまざまで、電柱1本の立ち位置でさえ国や自治体、あるいは民地の可能性もあります。
これらの業者・自治体・個人すべての同意を得るのは簡単ではありません。
なおかつ、周辺地域への影響も考慮する必要があります。
丁寧な説明でメリットだけを論っても、維持管理の不安や将来的な増税などが見え隠れしたり、胡散臭い利権が絡んでいたりしたら、住民が躊躇するのも無理はありません。
アフターを考慮した、誠意ある対応が必要でしょう。
電線地中化のメリットとデメリットは表裏一体
「電線地中化」で検索すると、「コストの高さ」がデメリットの筆頭に挙がり、「景観の美しさ」がメリットの一番目に提示されますが、こちらではあえて除外しました。
なぜならば、コスト問題は技術やアイディアによって改善される可能性が高く、資材費も時価に左右されるからです。
また、景観への賛美も個々の嗜好が反映されたり、時代によって移り変わったりします。
以下、電線地中化の3つのメリット・デメリットを表にしました。
| メリット | デメリット |
| 二次災害のリスクが減る | 浸水のリスクがある |
| 通行がスムーズになる | トラブル復旧に時間がかかる |
| 防犯に役立つ | 標識や防犯カメラを設置できない |
台風などによる電柱倒壊や断線の二次災害がなくなるのは大きなメリットです。しかし、電線が地中化されたからといって、必ずしも風水害による二次災害がないとはいいきれません。
事実、阪神淡路大震災のときは地盤の液状化が被害を拡大させました。
地盤問題は、「電線地中化」の最初に考慮すべき課題です。
電線をつなぐ電柱がなくなれば、歩道が広くなり通行が容易になります。
とはいえ、結局、歩道には標識が設置されます。防犯目的の監視カメラをどこに設置するかも悩むところです。
その一方で、電柱をよじ登って侵入する空き巣や、陰に隠れてコソコソするストーカーの被害がなくなる防犯効果もあります。
つまるところ、メリット・デメリットは表裏一体といえるようです。
日本での電線地中化を進める低コスト工法
近年、「電線地中化」の遅々とした歩みの反省から、最大の妨げとなっていた高コストへのさまざまな取り組みが試されるようになりました。
「電線地中化」の低コスト工法を3つご紹介します。
| 特徴 | メリット | デメリット | |
| 直接埋設 | ケーブルを直接埋設
海外で主流 |
かなりの低コストを実現できる
工事期間も短い |
断線の可能性が大きい
メンテナンスが困難 |
| 浅層埋設 | 浅い位置に埋設 | 狭小道路での施工可能
工事期間が短い |
ほかのケーブル損傷の怖れ |
| 小型BOX式 | 従来より小さなBOXで埋設 | メンテナンスしやすい | 施工性が低く手探りの状態 |
メリットもデメリットもあり試行錯誤の状態が続きます。
このほか、リサイクル部材の活用や、電力と通信のケーブル長を統一して施工するなど、さまざまなコストカット案が浮上しています。
また、「電線地中化」ではありませんが、「裏配線」や「軒下配線」も低コストで、比較的容易な工法です。
参考にしたい電線地中化のモデル地区
導入の進まない「電線地中化」ですが、自治体による地方創生事業としての観光客誘致、人口増加目的での街づくりとしての施工例は各地に散見されます。
それぞれに地形や道路事情など異なる中で、さまざまな妨げに屈せず施工されてきました。
自治体主導の「電線地中化」や住民有志の出資による施工など、いくつかの事例をご紹介します。
以下の表をご参照ください。
| 兵庫県芦屋市六麓荘町 | 1928年、日本で最初に電線地中化した街。高級住宅街 |
| 京都市南区・東寺前の国道1号 | 日本一高い五重塔の景観を電柱や電線に邪魔されず眺められる |
| 兵庫県姫路市・姫路城周辺 | 周辺地域の電線地中化により、姫路城の美しい景観を確保 |
| 鹿児島県天文館・城山地区 | 歴史的建造物周辺の電線を地中化し観光客に好評 |
| 大阪市阿倍野区再開発エリア | 再開発により電線地中化。街の雰囲気向上のため。 |
| 新潟県見附市ウエルネスタウン | 地方創生のモデル事業として「小型BOX」「浅層埋設」による地中化 |
| 京都市中京区先斗町通 | 狭小道路で電線が似合うともいわれていたが「小型BOX」にて地中化 |
まとめ
どのような事業であれ、メリット・デメリットはありますが、「電線地中化」工事におけるメリット・デメリットの両義性は顕著で、どちらとも捉えられます。
どちらとも捉えられるのであれば、国が推進し、国民の多くが望む方向へ進むのが望ましいのではないでしょうか。
懸念されてきたコスト問題も、工法やアイディアにより解決の兆しが見えてきました。
成功した美しい街の景観に惚れこみ、重い腰を上げる自治体や業者も増えています。
「電線地中化」の普及にいっそう拍車がかかるのを願います。