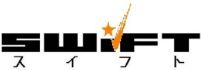コラム
column
不同沈下はどのような現象?発生のメカニズムと発生しやすい状態とは
2022年11月29日
日常生活を送る中で、窓が開けにくくなったりサッシの鍵がかかりにくくなったりしていませんか?
もしかしたら、それは「不同沈下」が原因かもしれません。
不同沈下とは何か、また発生のメカニズムについてまとめます。

不同沈下とは
地面の中では、さまざまな地質の土が層をなしています。
粘土層と呼ばれる粒子が細かい層や、砂礫層といった粒子が荒く水を含みやすい層などが折り重なっているのです。
例えば、砂礫層に含まれる水分を、井戸の設置により過剰に汲み上げることで、砂礫層が収縮し地盤が下がることがあります。
このような現象を地盤沈下といいます。
地盤沈下は土地全体が同じように沈み込むだけではなく、土地の一部分だけが沈み込む場合があります。
宅地でこのような一部分だけが沈み込むと、土地の上に建設された建物は傾くように沈みます。
これが不同沈下と呼ばれる現象です。
建物が傾くため場合によっては窓が開けにくくなったり、サッシの鍵がかかりにくくなったりします。
大きなダメージが発生する危険も
不同沈下が発生すると、建具の締まりがわるくなるといった不具合が起こるだけではなく、もっと大きなダメージが発生する危険もあります。
通常建物は、水平や垂直を保つことが前提で作られます。
ですが、不同沈下により建物が傾くと水平や垂直が保てず、構造体の一部分に過度な負担がかかってしまうのです。
その結果、隙間が生じたり基礎に亀裂が入ったりする場合が出てきます。
建物に隙間ができると、そこから雨水が入り込み構造体を腐食させる危険があります。
また、建物を支える基礎に亀裂が入れば、建物が倒壊する危険があります。
不同沈下が起こるメカニズム
建物倒壊というリスクまである不同沈下は、どうして起こるのでしょうか。
不同沈下が起こるメカニズムについて解説します。
荷重と地耐力
建築物を作るときには、通常建設予定地の地盤調査を実施し、建物の重量に対して地耐力に問題がないか調べます。
地耐力というのは、上からの圧力にどの程度耐えられる地面なのかを表したものです。
建物の重量に耐えられる地耐力がある地盤なら問題がありません。
ですが、地耐力が建物の重量に耐えられない場合、圧力に負けて地盤沈下が発生します。
地盤調査の段階で地盤沈下が起こりやすい軟弱地盤だと判明していれば、通常地盤改良工事を実施し地耐力を底上げします。
ですが、何かしらの理由で地盤調査していなかったり、地盤調査時点では分からなかった軟弱地盤があったりする場合があります。
建物建築後にこのような軟弱地盤の箇所が建物の重量に耐え切れず地盤沈下を起こすと、建物の一部だけが傾く不同沈下が発生するのです。
どうして軟弱地盤が分からなかったのか
地盤調査を実施していない場合に軟弱地盤の存在が分からないというのは理解できるでしょう。
ですが、地盤調査を実施しているのに軟弱地盤の存在が分からなかったといわれると理解できないかもしれません。
実は調査方法や調査箇所によって軟弱地盤が分からない場合もあるのです。
空隙があった
昔掘った井戸や浄化槽があった場所など、地盤調査によって発見できる場合とできない場合があります。
発見できていなかったこのような空洞や隙間があると、建物の重量に押しつぶされて地盤沈下が発生します。
不規則な軟弱地盤の存在
地中の地層は、必ず均一に層をなしているわけではありません。
例えば、地耐力が十分にある地層にくさび型に軟弱地盤があった場合は、調査地点によっては軟弱地盤に気付けない場合があります。
調査した場所では見つけられなかった軟弱地盤の存在で、地盤が建物の重量に耐え切れず地盤沈下が発生し不同沈下が起こるのです。
地盤改良の失敗
軟弱地盤の存在を把握していても、その土質を誤ってしまったために地盤改良の施工不良が起こる場合があります。
宅地の地盤改良では柱状改良工法で施工するのが一般的です。
この工法では、その土地の土にセメント系固化材を混ぜ込み補強材を作ります。
ですが、このセメント系固化材は酸性が強い土質を持つ土と混ぜると固まりにくい性質があります。
植物などが腐敗して作られた「腐植土層」が代表的な酸性の性質を持つ土質です。
安定した土質といわれる火山灰質粘土層でも、二次堆積といって盛土やがけ崩れなどで堆積した場合は黒ボクが堆積しやはり酸性の性質となります。
二次堆積の火山灰質粘土は、まばらに土の中に堆積している場合もあり、発見できない場合があるのです。
障害物があった
埋め立てにより造成された土地の場合、埋め立てた土の中にコンクリート塊や岩石などが含まれる場合があります。
地盤調査の際にこれらが障害物となり本来の地盤よりも高い地耐力を検出してしまう場合があります。
近隣の工事が影響する場合も
地盤調査や地盤改良が正しく実施されていたとしても、近隣で実施された工事の影響で不同沈下が発生することもあります。
例えば、近隣で盛土があった場合、地面の上からの圧力が増え地盤沈下が発生します。
また、地盤の掘削や地下水の過剰な汲み上げでも地耐力が下がります。
まとめ
家が傾く「不同沈下」は、一部分の地盤沈下により発生します。
原因としては地盤調査で見つけられなかった軟弱地盤や空隙の存在があったり、障害物となる異物が混入していたりするためです。
また、近隣での盛土や掘削工事が原因となる場合もあります。
建具の開閉がしにくい、外壁や基礎に亀裂があるなど異変が生じていたら、不同沈下が発生していないか調査することをおすすめします。