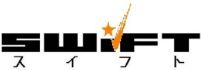コラム
column
柱状改良が設計上必要に!そもそも柱状改良とは何?
2022年11月08日
住宅建設の際、つい上物である「建築物」に注目しがちです。
ですが、設計計画書には建築物以外についても、様々な記載事項があります。
記載事項の中には「柱状改良工」という記載があるかもしれません。
これはどのようなことなのかをまとめます。

地盤
土地の上に建設する建物は、平均的な木造2階建ての住宅でも約30トンの重量があります。
この重量を受け止められるだけの強い地盤がなければ、建物が傾いたり沈んだりします。
また、最悪のケースでは土地が崩れてしまう場合もあります。
結果として建物も倒壊する危険があるのです。
このため、建物の重量を受け止められない地盤の場合、地盤改良工事を実施します。
地盤改良工事の種類
地盤改良工事は、地盤の状態に合わせ複数あります。
その中から適切なものを選び、地盤補強していきます。
代表的な物には、次の3種類があります。
・表層改良工法
・柱状改良工法
・小口径鋼管杭工法
つまり柱状改良工法というのは、地盤改良工事の一つです。
柱状改良工法を中心に、三種類の地盤改良工事の特徴も解説します。
表層改良工法
表層改良工法は、その名前の通り地面の表面部分に施される改良工事です。
地盤の軟弱な部分が地表から2m程度に限られる場合は、表層部分を掘削してセメント系固化材を混ぜた土で締め固めます。
小口径鋼管杭工法
軟弱地盤に鋼管杭を打ち、地中から建物を支える工法です。
地中30mまでの地盤補強が可能で、地中の固い地盤にまで鋼管杭を打ちます。
工期が短く、狭小地でも工事が可能な地盤改良工事です。
柱状改良工法
一般的な宅地の地盤改良工事では、この柱状改良工法によるものが多くなります。
地上3階以下、さらに高さ13m以下の建物で、軒高が9m以下、延べ面積500平米以下の小規模建物や、中規模建築物に適用されます。
砂質土や粘土質の地盤改良が可能です。
最大改良長は12mで、改良径は400~1,200mmです。
工法の特徴
地盤改良したい土地の土と、セメント系固化材を使い地盤内に柱状の補強体を作ります。
地盤の強さや建物の重さなどに応じて何本の補強体を作るかが変わります。
改良径というのは、補強体となる柱の太さ、最大改良長は柱の長さと考えると分かりやすいでしょう。
最大改良長は12mとなっていますが、実際には2~8m程度の深さまで軟弱な地盤がある場合にこの工法が用いられます。
5~10m程度軟弱地盤がある場合には小口径鋼管杭工法が適用となります。
補強体は杭基礎とはことなり建物の基礎にはなりません。
建物が傾いたり沈んだりするのを防ぐ目的で施工します。
費用
表層改良工法では1坪あたり1~2万円程度、小口径鋼管杭工法で1坪あたり4~6万円程度費用が必要です。
柱状改良工法では1坪あたり2~3万円程度とちょうど中間の費用負担と考えると良いでしょう。
平均的な戸建ての延べ床面積が30坪程度ですので、柱状改良工事は50~80万円程度かかります。
メリット
地中2mよりも深い位置まで軟弱地盤がある場合でも、小口径鋼管杭工法に比べ、低価格で工事が可能です。
このため、宅地の地盤改良工事としては、一般的に施工されています。
杭を打つ工法では杭の先端を、固い地盤をもつ支持層まで到達させる必要があります。
ですが、柱状改良杭の場合には支持層まで到達できなくても施工可能なケースもあるのです。
これは柱状改良杭の軸径が大きいためで、補強体の周面摩擦力が大きいためです。
デメリット
その土地の土とセメント系固化材を混ぜ合わせ補強体となる柱を作る工法が柱状改良工法です。
そのため、土地の地質によっては柱状改良工法の施工ができない場合もあります。
適用となるのは砂土質や粘土質の土質をもつもので、有機質土の場合は柱状改良工法の施工はできません。
これはセメント系固化材が固まらず、固化不良が発生することがあるためです。
固化不良が起こると建物を支えられないだけではなく、六価クロムという有害物質が発生する危険があるためです。
六価クロムは発がん性物質の一つで、土壌汚染対策法により特定有害物質に指定されています。
有機質土の他、火山灰質粘性土も固化不良が発生する危険があります。
地中にセメント系固化材を混ぜた補強材を埋め込むこの工法では、原状復帰も難しくなります。
固化させた補強体を取り除く費用が掛かるため、賃借地では施工が難しいでしょう。
また、将来売却する希望がある場合は、土地価格の低下の懸念があります。
柱状改良杭の軸径も多いため、狭小地では施工できない場合もあります。
まとめ
柱状改良工法は、軟弱地盤状に建物を建てる際に実施される地盤改良工事の一つです。
一般的な地盤改良工事の一つで、多くの宅地の地盤改良に使われています。
そのため、施工可能な業者は多いのですが、一方で施工経験や技術の差が出やすい工法です。
また、施工後取り除くことが難しく、一部の地質では施工できない場合もあります。
施工にあたっては十分な検討が必要でしょう。